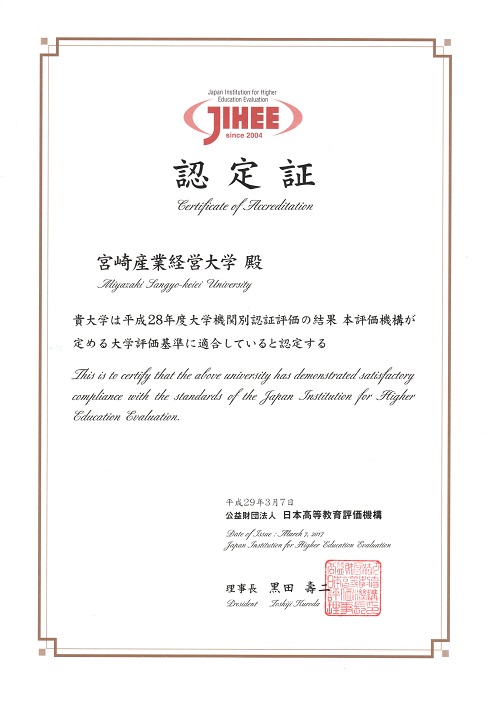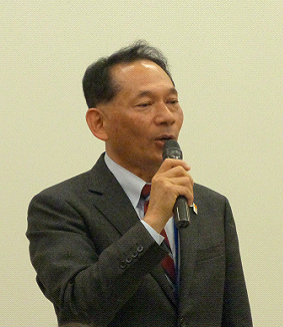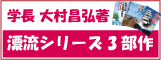経営学部合同ゼミナール(宮永,本田,森田,出山,日髙,柚原)による
「株式会社宮崎太陽キャピタル」研究視察報告!
去る平成28年12月19日(月)及び平成29年2月6日(月)の2回に分けて,本学経営学部の会計・金融系ゼミナール(以下,ゼミ)を中心とした宮永雅行ゼミ(投資教育,経済教育,FP教育),本田信雄ゼミ(財務管理論,企業財務論,証券投資論),森田英二ゼミ(情報システム論,会計学),出山実ゼミ(財務会計論,情報会計論),日髙光宣ゼミ(広告論,マーケティング・コミュニケーション論,流通論),柚原知明ゼミ(経営組織論,経営戦略論)は,「株式会社宮崎太陽キャピタル」(以下,「宮崎太陽キャピタル」)様に対して総参加人数70名規模の合同ゼミによる研究視察を行ってきました。
本研究視察は,宮崎県を代表する直接金融機関であるベンチャーキャピタルとしてベンチャー企業への投資,経営コンサルティング,各種産官学の連携事業等を行っている「宮崎太陽キャピタル」様の事業内容に関する経営実態と投資スキームの学習を目的として実施いたしました。
「宮崎太陽キャピタル」様におかれましては,大変お忙しい中参加者が総参加人数70名規模の私たちの研究視察のお受け入れ準備とご対応をいただきました。代表取締役社長の工藤広太様をはじめとするご対応いただいた社員の皆様に篤く御礼申し上げる次第でございます。
本研究視察に関しては,下記の通り1.研究視察日時・訪問先・ご対応いただいた方々,2.写真集,3.参加したゼミ学生の感想,4. 柚原知明教授の研究視察総括,についてご報告いたします。
記
1.研究視察日時・訪問先・ご対応いただいた方々
| ○研究視察日時(主対象ゼミ): |
平成28年12月19日(月)14:00~15:30
(宮永雅行ゼミ,本田信雄ゼミ,柚原知明ゼミ)
平成29年 2月 6日(月)14:00~15:30
(森田英二ゼミ,出山実ゼミ,日髙光宣ゼミ) |
| ○訪問先(所在地住所): |
「株式会社宮崎太陽キャピタル」
(宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 宮崎太陽銀行内) |
○ご対応いただいた方々:
代表取締役社長 工藤広太 様
業務部ベンチャー投資グループ Manager 津野省吾 様
業務部ベンチャー投資グループ Assistant Manager 金丸直史 様
2.写真集
写真1. 第1回目訪問時(12/19(木))の冒頭,私たちの訪問に対する歓迎のご挨拶をいただいた代表取締役社長の工藤広太様です。
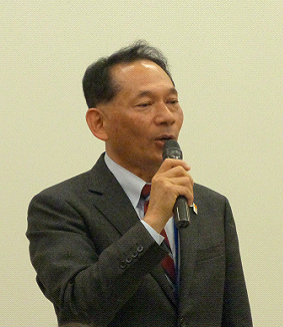
写真2. 第1回目 12/19(木) 金丸直史様の「ベンチャーキャピタルの業務について」を一所懸命に聞く学生達です。ベンチャーキャピタルという業界のアグレッシブかつエキサイティングな事業内容に大きな衝撃を受けたと思います。

写真3. 第2回目2/6(月)宮崎太陽キャピタル様への研究視察の様子です。金丸直史様の説明を聞き入る学生たち。フレンドリーに話しかけるように講演していただきました。

写真4. 質疑時間に積極的に質問をする岡原良奈さん(経営学部3年生)です。

写真5. 最後にゼミ学生全員を代表して、大坪冬輝くん(経営学部3年生)が今回の研究視察のお受け入れと講演に関する御礼を述べました。大変立派な御礼の挨拶でした。

3. 参加したゼミ学生の感想
東条晴香さん(経営学部2年生 森田英二ゼミ)
宮崎太陽キャピタル様にて,ベンチャーキャピタルについてお話を伺いました。そこで,ベンチャー企業が目標に向かっていくことを支援するというハンズオン支援に特に興味を持ちました。そして我々と同じ大学生も起業している現状など,自分が知らないことを多数お話ししていただきました。今回の研究視察は,大変貴重な時間になりました。
岩本幸直くん(経営学部2年生 本田信雄ゼミ)
今回,「株式会社宮崎太陽キャピタル」様を訪問させていただきました。そこで,ベンチャーキャピタルの仕事内容について説明を受け,初めはとてもリスキーなものだと感じましたが,実際こういう企業がないと,革新的なアイデアがあっても,それを実現させることは困難だと感じました。さらに,こういう夢のある人の背中を押す仕事は,とても魅力あるものだと思えました。
最後に,今回の企業見学で,普段学べない事を多く学ぶ事ができ,大変良い経験になりました。自分も人の役に立つことを見つけられたらと思いました。
本吉優介くん(経営学部2年生 宮永雅行ゼミ)
今回訪問した宮崎太陽キャピタル様については,地域に密着した企業支援に取り組んでいることに感銘を受けました。
工藤広太社長からは,「宮崎県では,少子化問題に加え若者の県外流出が激しいために地方経済が停滞する悪循環を生んでおり,会社としては起業家育成に携わることで学生ベンチャーによる地方創生を目指している。」というお話がありました。具体的には宮崎太陽キャピタル様の用意する数種類のハンズオンプランで起業家を支援していくというものですが,私はその内容に大変感心しました。近年メディアなどで学生起業家の活躍を目にする機会が増えているのもベンチャーキャピタルの支援があってこそだと思います。今回の訪問で自分の将来にも可能性を感じました。
細川静哉くん(経営学部3年生 出山実ゼミ)
今回,宮崎太陽キャピタル様のお話を聞かせていただいて,ベンチャーキャピタルについて,またそれらに関する知識や実際の業務などについて知ることができました。実際の事例や具体的な数値等を拝見させていただき,実際の投資,ベンチャーキャピタルについてイメージすることができ,それと同時にその難しさや成功,貢献できた際の達成感なども感じられました。また,宮崎太陽キャピタル様は地域,地元企業への思いが大きく,ここに住む我々にとって,身近で大きな存在であることを知りました。そして,宮崎に限らないことだとは思いますが,経営者,起業をしている方々の悩みが「自分以外に相談相手がいない」ということが共通していて,深刻であることが意外で驚きました。そんな悩みの相談相手も受付け,成長性を見込んでは投資し,その報酬として出資者の方々にお返し,還元していく,そんな宮崎太陽キャピタル様をとても素晴らしい企業だと思いました。
小玉智也くん(経営学部3年生 宮永雅行ゼミ)
私たちは,ゼミナールの講義の一環で先日「株式会社宮崎太陽キャピタル」様を訪問させていただき研究視察を行いました。
宮崎太陽キャピタル様では株式出資や企業のコンサルティングなど幅広い業務を行っており,大変有意義なお話を聞くことができました。
日ごろ銀行には「融資」のイメージが強く,ベンチャーキャピタルの実態をあまり知らなかったため,「企業の株式でキャピタルゲインを出す」ということはなかなか新鮮でした。ご説明の中では,過去投資した企業の中に最近株式市場へ上場した事例報告等もあり、自分たちの身近にある企業の話が聞けて良かったと思います。また,宮崎太陽キャピタル様では学生ベンチャーの支援にも力を入れているということで,少し起業するということについても興味が湧きました。
古川大樹くん(経営学部4年生 柚原知明ゼミ)
今回の研究視察が行われることを聞いたときから,ベンチャーキャピタルの話が聴けるということで楽しみにしていました。ベンチャーキャピタルの仕組み,融資と投資の定義や違い,みやざき未来応援ファンドが13社に投資していること,具体的な成功・失敗事例などを学ぶことができました。新規株式上場に関連する用語も出てきて,復習という意味でも有意義な研究視察になったと感じています。融資とは,一定の金利を付けてお金を貸すことで,決算書を見て妥当か否か判断します。一方,投資とは,投資先企業における株式の一部を購入することで,事業の将来性や成長性を踏まえて妥当か否かを判断します。私は,宮崎太陽銀行京塚支店さんに時々行きます。これからは,今回学習したことを踏まえながら,宮崎太陽銀行様を利用しようと思います。ご対応いただいた宮崎太陽キャピタル様における代表取締役の工藤広太様,津野省吾様,金丸直史様に深く御礼申し上げます。
4.柚原知明教授の研究視察総括
「ベンチャーキャピタル(venture capital,以下VC)」という直接金融(投資家と企業が直接的に関わる金融の仕組み)機関の事業内容について考えてみたいと思います。
間接金融(投資家と企業との間に銀行等が間接的に関わる金融の仕組み)機関である「銀行」が行っている主な業務の中心は,預金者から預かった資金を企業や個人等の様々なお客様への融資によって利息を得ることで事業運営を行っております。融資を受けた企業においては,当該企業の貸借対照表(B/S)上において他人資本(負債)となり,期日までに融資を受けた金額(借入金)に利息をつけて返却しなければなりません。融資を行う「銀行」においては,融資先企業が期日までに間違いなく返却出来るかという“経営の安定性や健全性”を中心とした与信の審査を行います。
一方の直接金融機関であるVCの主な業務の中心は,株式市場に上場していない未上場の有望企業に対するハイリターンを狙ったアグレッシブな投資です。また,VCの業務には投資に際して外部の投資家(機関と個人含む)の資金を集めたファンド(fund,複数の投資家から集めた資金を投資し,そのリターンを分配する仕組み)を組織化し,その資金を有望企業に対して投資を行う「外部資金の運用受託機関」としての側面も有しております。VCは,主に投資先企業の株式の一部を引き受けて,その株式と引き換えに投資を行います。投資を受けた企業においては,当該企業の貸借対照表(B/S)上において自己資本となり,VCが当該企業の株主として所有者の一部となります。投資後のVCによっては,企業価値の向上を目指した積極的な経営への支援(hands-on)として経営コンサルティングや役員の派遣を行う場合も存在します。VCにおける投資の出口(exit)としては,企業価値の上昇後に向けたIPO(initial public offering,新規株式上場)やM&A(mergers and acquisitions,合併と買収)等が検討されます。投資を行ったVCにおいては,投資額と引き受けた株式の売却額との差額が利益(capital gain)となります。従って,投資を行うVCにおいては,投資先企業における業績や企業価値に関する“経営の成長性や将来性”が審査の際に重要となります。融資を行う銀行と投資を行うVCには,審査基準に本質的な違いが存在するのです。
今回の「宮崎太陽キャピタル」様への研究視察においては, VCにおける実際の投資スキームとその実績についてお話を伺うことができました。書物や文献だけでは学べない,莫大な利益(莫大な損失含む)を得ることが出来る非常にエキサイティングな投資の世界に関する内容でした。特に様々なリスクやトラブルを考慮した投資契約の在り方,投資先企業における資本政策(capital policy)の策定や指導,剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会の議決権等に関わる種類株式における優先株式(preferred stock)を活用した投資スキーム,株式のみならず社債を活用した投資等は,座学だけで修得できる内容ではありません。優れたベンチャーキャピタリスト(venture capitalist)には,数々の厳しい修羅場を乗り越えてきた実績,及び豊富な実務経験をベースとした分析力や洞察力が求められます。日本は,投資に関して世界の先進諸国と比較すると法制度をはじめとする社会的な仕組みや国民の意識(元金保証が前提)が後進国の実態にあります。今回参加した学生諸君の中には,将来起業家や投資家になりたいと夢見るきっかけになった方も居ると思います。学生諸君は,今回の研究視察を機会として日頃学んでいる簿記論,会計学,マーケティング論,経営戦略論,IT関連科目等を一体何のために学ぶのかについて考えてほしいと思います。ぜひ,志のある学生諸君は大学でしっかりとした理論を勉強して,実社会での厳しい実務経験を積んで,将来憧れの起業家や投資家になってください。
私たちの学んでいる経営学という社会科学は,物理学や化学のような自然科学と違い理論の検証や体系化に向けた実験が難しい学問領域です。しかしながら,社会活動や経営活動の現象・実態把握に関する測定を含む観察については,対象企業や組織のご協力をいただくことである程度可能となります。経営学の学徒(教員含む)にとっては,理論をある程度学んだら,積極的に実際の現場に出て行って取材や観察(研究視察)をすることが再び理論を学ぶ新たな興味や問題意識を醸成させます。経営学の発展においても,理論と実態との相互学習が非常に重要となります。
最後になりましたが,私たちの受け入れ準備と丁寧なご対応をいただきました「宮崎太陽キャピタル」代表取締役の工藤広太様をはじめとする社員の皆様に篤く御礼申し上げる次第でございます。
以上
(編集 経営学部/出山実)